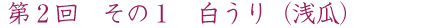 |
白うりはメロンやマクワウリと同種の瓜で平安時代から使われている食材です。京都産の白瓜は桂瓜と呼ばれ、奈良漬になります。
浅瓜と呼ばれる小振りな白瓜は調理方法が伝承されにくく店頭から消えつつあります。見かけたら是非使ってみてください。 |
|
「雷干し」 |
|
① 瓜に上下を切り落とし、種を抜いて、皮のままらせん状に切る。 |
② 立塩(水1カップに塩大さじ1杯)にしばらく漬けてザルに取り、水気をふく。
|

|
| ③ 瓜の端に串を通して串の両端にひもを付けてつるし、軒下で一日干す。現在はザルに入れて一日陰干しするか、冷蔵庫に入れて表面を乾かす方法でもいい。 |
| ④ 一口大にちぎって削り節と少々の醤油をかけておかずに、茶事の八寸の山のものに、朝茶事の香物などに用います。 |
※「雷干し」の名の由来は、らせんの形状が雷神のもっている太鼓に似ているからとか、雷の多い時期に作るからという説があります。私は、かむとバリバリと音の出る歯ごたえ(食感)が雷神の到来のようで、胸がさわぐのです。
素朴で乙な味わいの一品で、夏に一度は作ってみたいものです。 |
|
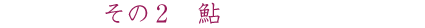 |
鮎は夏を代表する優美な姿の川魚で、こけを食べて成長するので香魚と呼ばれ、特に腹わたがおいしい。天然の鮎は一般的に塩焼きにして蓼酢でいただきます。現在この鮎は入手が難しくなってきました。市販の鮎は養殖池でふ化し、6~8cmに達した頃に、川に放流して出荷します。 |
|
(鮎の風干し) |
|
|
| ① 鮎は三枚におろして腹骨をすき取り、立塩に漬けて暫くおき、水けをふき取って身の尾側に串を通してつるし、(瓜と同様)風通しの良い所で一夜干しする。(ザルに並べて冷蔵庫で乾かしても良い) |
| ② 酒を塗ってあぶり、片身を二つに切る。 |
③ 酒の肴、朝食のおかずに、朝茶事の向付に、八寸の海のものに用います。 |
| |
|
|
| ※古代、権力のある女性は巫女的存在で神意を問う祈(うけ)いは重要な役目でした。説話によれば神功皇后が新羅に出兵する際も祈いをしました。自身のまとっていた裳(もすそ)の糸を抜き取って針をつけ飯粒を餌にして川に沈め魚つりをしました。この時珍しい魚がつれ、これが鮎だった。(黒岩重吾氏)
※魚へんに占と書くのはこの頃からでしょうか。昔から今も皇室の慶事に出される魚は鮎です。鮎は昔から位の高い食材です。 |
| |
