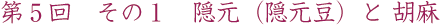 |
| 隠元 |
隠元はアメリカ原産で1654年に中国(明)から来日した隠元禅師によってもたらされました。
日本には200種類程ありますが、私達が甘納豆や白あんとしておなじみの大きな白い豆をつける果実を食べる種類があります。
今回使う隠元は若いさやを食べる種類で「さやいんげん」と呼ばれています。さやいんげんは年に3度収穫することができるので、関西では三度豆と呼ばれています。
|
|
さやいんげんの胡麻和え |
 |
| |
材料(4人分 )
|
| |
いんげん |
・・・ |
200g |
| |
白いり胡麻 |
・・・ |
|
| |
砂糖 |
・・・ |
小2 |
| |
醤油 |
・・・ |
大 1 |
| |
いり胡麻 |
・・・ |
少々 |
|
|
|
|
| |
 |
 |
① いんげんは色よく茹でて冷水にとり、水気をとって斜め3つに切る。 |
② いり胡麻はフライパンを温め、火を止めてその中にいれ、さらさらと振り、パリッとさせる。 |
③ すり鉢でよくすって調味料を加え、再びすって①を和える。(写真2) |
④ 盛りつけたら上に胡麻つぶをぱらりとかける。(写真3) |
| |
※生胡麻の炒り方
「3粒はねたらいいのよ」と母が言う。
※胡麻のすり方
胡麻はすり鉢でするのが一番おいしい。
力を入れてよくすると香りや甘味、旨味、油が出てしっとり、こくのある衣となります。 |
|
| 胡麻 |
胡麻はエジプト原産といわれていますが、栽培は古代インドで始まりました。
テレビコマーシャルなどで有名なセサミンに代表されるゴマリグナン類は健康増進機能が注目されています。他に必須アミノ酸などを含有していますが、胡麻の80%は良質な脂質(オレイン酸・リノール酸)を含んでいます。これらの油は緑黄色野菜のβカロテンをビタミンAにするのに必要です。
母はほうれん草やつる菜など「畑のおいしくないものは胡麻で和えると美味しくなるのよ」と言っていましたが栄養知識のない時代に化学的に調理していたと感心します。
現在「ごまかす」の言葉の意味にもなっています。 |
|
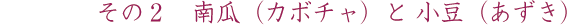 |
カボチャはアメリカ原産ですが、いろいろな種類があります。表面がでこぼこしていて水っぽい日本カボチャは戦国時代に渡来し、私達が日常使っているほくほくしたクリカボチャは江戸時代末期に渡来しました。
武田信玄の陣中食に「餺飥(ほうとう)」があります。きしめんの太いようなもので、熊肉や野菜を入れて味噌で仕立てた鍋物です。「うまはずだよ、カボチャのほうとう」といわれ、戦国時代に九州に渡来した珍しいカボチャを甲斐の国で食すことはとても御馳走であったのでしょう。今でも甲府、諏訪のあたりでは「カボチャのほうとう」が有名です。 |
|
南瓜のいとこ煮 |
 |
| |
材料(4人分 ) |
| |
南瓜 |
・・・ |
350g
|
| |
小豆 |
・・・ |
1/2カップ |
| |
だし |
・・・ |
1カップ |
| |
砂糖 |
・・・ |
大4 |
| |
塩 |
・・・ |
小1/4 |
| |
醤油 |
・・・ |
小1 |
|
|
|
|
| |
 |
 |
| ① 小豆は洗って一晩水に浸しておき、火にかける。煮立ったら汁を捨てて再び水を入れて火にかけ、柔らかく茹でる。冷めるまでおき、笊に上げる。 |
| ② 南瓜は2.5cm角に切り、だしを入れて火にかける。煮立ってきたら砂糖を入れ、5分位したら塩と醤油を加え、少したったら小豆を加え、落とし蓋をして南瓜が柔らかくなったら火を止める。 |
| ③ 小豆の缶詰を利用するのも良いでしょう。 |
| |
|
| |
※いとこ煮の名の由来
冠婚葬祭には甥、姪というような「いとこ」が集まります。近い関係の野菜同志という意味でこう呼ばれるそうです。昔から神仏に供えた野菜を固いものから順においおい(甥)、めいめい(姪)と入れて煮たといいます。代表的なものが「南瓜のいとこ煮」です。 |
|
小豆(あずき) |
あずきはアジア原産で日本ではあずきの赤い色が邪気を払う力(魔よけ)があるとしてお祝い事(赤飯)などによく使われます。
小粒(少納言)から中粒(普通、小豆=中納言)、大粒(大納言)と分けられ、汁粉やぜんざい、あんなどに使われます。
茶懐石では開炉や初釜の味噌汁の具として大納言が使われたりします。 |
