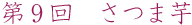 |
さつま芋は中央アフリカ原産といわれ、大航海時代にヨーロッパに伝わり、我が国へはスペインから琉球経由で17世紀初めに薩摩と平戸に伝わりました。荒れ地でも出来る優れた作物として青木昆陽らによって広められ、急速に普及しました。
細いベニアズマやずんぐり型の高系14号は皮が赤紫色、肉がクリーム色で青果用として多量に生産されています。皮が赤くて細く、加熱すると肉が濃い黄色になる金時はきんとんやあんに向きます。肉が白いコガネセンガンは焼酎に向きます。また肉まで紫色の綾紫や山川紫はアントシアニンの色を生かして菓子等に加工されます。
成分は糖質のうち約8割が澱粉で、しょ糖、ぶどう糖、果糖などが他の芋類より多く甘味があります。又、食物繊維もあり、ビタミンB1、C、Eも多く特にビタミンCは加熱しても壊れにくい質を持っています。ゆっくり温度を上げるとβアミラーゼが作用してさつま芋中の澱粉が麦芽糖などに分解されて甘くなりますが、電子レンジで急速に加熱すると酵素が充分に作用せず甘さが少なくなります。 |
|
栂尾煮(とがのおに) |
今回はゆっくり加熱して甘くて美味しい栂尾煮を作りましょう。
栂尾煮はさつま芋を砂糖で甘く煮た料理のことです。京都府栂尾の高山寺で精進料理に用いたのが始まりといわれています。質の良い大きな金時がいいですね。 |
 |
|
材料(4人分)
|
さつま芋 |
・・・ |
300g |
| みょうばん水 |
|
|
|
焼きみょうばん |
・・・ |
小1/2 |
| 水 |
・・・ |
2C |
| くちなしの実 |
・・・ |
1~2個 |
| 砂糖 |
・・・ |
大3 |
| みりん |
・・・ |
大1 |
| 塩 |
・・・ |
少々 |
| 枝豆 |
・・・ |
正味1/3C |
|
|
|
| |
① 枝豆は茹でて薄皮をむく。
② さつま芋は2cm厚さの輪切りにして皮をむき、みょうばん水に浸けてアクを抜く。
③ くちなしの実は斜め半分に切ってガーゼに包む。
④ 大きめの鍋によく洗ったさつま芋とくちなしを入れ、水をたっぷり入れて芋に火が通るまで煮る。 煮汁がまだ充分ある頃くちなしの実は取り出し、砂糖を加えてしゃもじで混ぜ、芋を半つぶししてほっくりの状態に仕上げる。枝豆を入れて彩り、みりんでつやを出し、塩で味を整える。(枝豆は入れなくてもかまいません。) |
| |
|
|
~小話~
「栂尾煮ってどういう煮物ですか」と問うと、師匠は「栂尾には黄色のさつま芋が取れたから」との答えです。京都在住の友人に電話で尋ねると「まさか、自然薯ならあるかもね、さつま芋など取れる所じゃないわよ。」との答えです。
夫を誘い紅葉真っ盛りの栂尾を訪ねることにしました。行く先は高山寺。「帰りのバスは渡月橋を通るので橋の袂で貴方の好きな桜餅が買えるから行ってね。」と説得しての取材旅行です。行く手は想像以上の北山杉で黄葉・紅葉はちらほらと彩る程度。でも深山ゆえのマイナスイオンを満喫しながらのゆったり旅です。
高山寺の山門をくぐると明恵(みょうえ)上人ゆかりの茶園が現存しているのにまずは感動しました。
この茶園は鎌倉時代、栄西禅師に参禅修業していた明恵上人が栄西禅師から茶の種子をもらって植えたもので、この茶の木は高山寺で育って本茶となり宇治に移植されて宇治茶の繁栄となりました。私達が常に使っている抹茶(碾茶〈てんちゃ〉)の主な生産地なのです。寺院の中に入るとガラスケースの中に鳥獣人物戯画が飾られていました。平安時代に京ではやった田楽踊りを風刺したものです。料理のおでん(御田=田楽)にかかわりのあるものでもあります。
さつま芋を訪ねやって来ましたが、山また山のこの地方はやはりさつま芋の産地ではありません。さつま芋がもたらされたのは前記のとおり江戸時代ですから 明恵上人が開山(1206年)してからずっと後のお話です。当時はさつま芋も砂糖も珍しい貴重なものでしたから食べた客人はさぞびっくりしたことでしょう。このお料理を栂尾煮と名付けたのです。現在この料理法を用い進化させたものに「きんとん」や「スイートポテト」があります。
さて帰りのバスは2時間遅れでやって来て超満員。立ち続けて2時間がかりで、嵐山に着いたのは夜です。桜餅どころではありません。あわただしく京都駅へ。新幹線の中で夫は「もう行ってやらない」とぷんぷん。申し訳ないと思う一方で私にとって得る事の多い旅だったと思うのでした。 |

