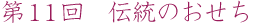 |

|
|
お正月を迎える準備をします。門松、しめ縄は一般的に28日から7日まで飾ります。鏡餅は三方にのせて床の間に置き、半紙を四方にたらして敷いて、上に昆布を前に、裏白とゆずり葉を左右に出るように置き、重ね餅をのせ、上に紙垂(しで)と輪じめ、橙(だいだい)を飾ります。
裏白は心の裏まで潔白。ゆずり葉は栄えた家業を子孫に譲る。昆布は喜ぶ。重ね餅は豊作と夫婦円満。紙垂は清浄。輪じめは依代(よりしろ)。橙は代々の繁栄を意味します。 |
| |
 |
豆金団 |
|
|
材料(4人分~10人分)
|
白甘納豆 |
・・・ |
200g |
| 白あん(生) |
・・・ |
400g |
| 水 |
・・・ |
1C |
| 砂糖 |
・・・ |
300g |
| みりん |
・・・ |
大4 |
| 塩 |
・・・ |
小 1/5 |
 |
*白隠元豆の甘煮200g~400g
同窓の内藤あんこ屋さんで求めてください。 |
|
|
|
①白甘納豆は少量の湯をかけておく。(甘煮ならそのまま)
②砂糖と水を煮立て、白の生あんを入れて、柔らかめに練り、塩を入れて味を調え、みりんを入れて艶を出し①を混ぜる。
|
|
①鶏ひき肉200g、卵1/2個、しょうゆ大さじ1、砂糖小さじ1/2、片栗粉小さじ1をよく練り、天板にかまぼこ状にして200度の天火で15分焼く。
②ゆで卵6個を卵白、卵黄に分けて裏ごし、おのおのに砂糖大さじ3と塩少量を入れて混ぜる。スダレの上にぬれ布巾を敷き、卵黄を①の肉が一巻きできる大きさに伸ばし、上に卵白を重ね、肉を芯にして巻く。
③スダレのまま7分蒸し、冷めてから1~2cm厚さに切る。 |
小鯛の笹ずし |
①米2カップを炊き、合わせ酢(酢大さじ3、砂糖大さじ2、塩小さじ1と1/2)をかけて冷ます。
②小鯛の笹漬け一樽を求め、片身を一つの握りずしにして、笹の葉で巻く。 |
|
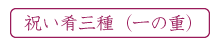 |
|
お正月に飲む屠蘇は「お屠蘇気分」と言われるほどの祝い酒で、邪気や病気を払い、家族の健康を祈願して元旦から三日まで飲みます。屠蘇器に屠蘇散と酒、またはみりんを入れて薬酒を作ります。屠蘇散は山椒(さんしょう)、肉桂(にっけい)等の薬草が入ったものです。わが家では、子供が幼いころはみりんを入れ、成長するにつれてお酒を増していきました。杯は三段重ねになっていて年の若い人から順に飲みます。
屠蘇の祝い肴(さかな)は黒豆、田作、数の子で年始客にこの三種を盛って出します。 |
 |
 |
黒豆 |
|
|
材料(8人分~24人分)
*5合(5C)が作りよい。沢山たいて親や子や友人にプレゼント。
|
黒豆(新物) |
・・・ |
5C *増井商店、北海道産がおすすめ |
| 湯 |
・・・ |
12 C |
| 砂糖 |
・・・ |
500g |
| しょうゆ |
・・・ |
1/2 C |
| 塩 |
・・・ |
大1 |
| 重曹 |
・・・ |
小1 |
| 太いさびクギ |
・・・ |
大5本 |
 |
|
|
|
①鍋で分量の湯をわかし火を止めて、調味料を加え、溶けたら重曹とクギを入れる。
②豆を洗って笊に上げ①の熱い汁の中に入れて5時間おく。
③②を火にかけ、沸騰したら火を弱めてアクをすくい取り、差し水1/4カップを加え、落とし蓋(和紙)をして弱火で2~3時間煮る。程良い柔らかさに煮上がった時、煮汁が豆とひたひたの状態が良い。 |
|
①ごまめ100gは小分けしてフライパンでからっとするまで弱火でいる。
②笊に取って振り、焼けかすを除く。
③フライパンに砂糖大さじ1、しょうゆ、みりん各大さじ2を入れて少し煮詰め①を加えて手早くかき混ぜ、照りをつけて大皿に移す。 |
数の子 |
①数の子12本は、塩けがやや残る程度に塩抜きして、薄皮を除く。
②しょうゆ、酒、だし各1/3カップを沸騰させて冷まし①に漬けこむ。 |
|
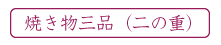
|
|
おせち料理は節句に食べるものでしたが、現在はお正月料理のことを指します。正月三が日分を暮のうちに用意します。日ごろ、忙しい主婦を家事から解放するための料理で、保存のきくように味付けして重詰めにします。肉、魚、野菜、乾物を使い、栄養のバランスもよく、色彩豊かで、伝統を踏まえた縁起の良い料理は古人の知恵のたまものです。
重箱は正式には五段重ねで、上から一の重(酒肴、口取り)二の重(焼き物)三の重(煮物)与の重(酢の物)五の重(控え重)です。詰め方は、味が混ざらないように工夫します。 |
 |
 |
小判つくね |
|
|
材料(4人分~12人分)
|
豚ひき肉 |
・・・ |
200g |
| ジャガイモ |
・・・ |
1個 |
| にんじん |
・・・ |
30g |
| 小麦粉 |
・・・ |
大2 |
| 卵 |
・・・ |
1/2 個 |
| しょうゆ |
・・・ |
小2 |
| 砂糖 |
|
小2 |
| 煮汁 |
|
しょうゆ |
・・・ |
大3 |
| 酒 |
・・・ |
大3 |
| 砂糖 |
・・・ |
大5 |
| 水 |
・・・ |
大5 |
 |
|
|
|
①ひき肉に、ジャガイモのマッシュとにんじんをみじん切りにして小麦粉をまぶしたものと、卵、調味料を入れて、よく練り混ぜる。
②12個の小判形に丸めて、フライパンで両面を少し焦げ目がつく程度に焼く。
③フライパンに調味料を煮立て、②を並べ入れ、中火で煮込み、汁をからませる。
|
|
①12切れの切り身(500g)は柚子1個分の輪切りと酒、みりん各1/4カップ、しょうゆ1/2カップの幽庵地に3時間以上漬けてから焼く。途中みりんを塗り、照りを出す。 |
帆立貝ウニ焼き |
①練りウニ大さじ2に卵黄2個を混ぜておく。
②生貝柱12個を天板に並べ200度で3分焼いてから①を上に塗って、再び2分焼く。 |
|
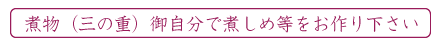 |
|

|
|
除夜の鐘。百八もあるといわれる人間の煩悩の消滅を祈って突く鐘です。鎌倉時代に禅寺で朝夕行われていたのが、室町時代からは大みそかに突くようになったと聞きます。静かなこの夜の梵鐘の音は、心に深く響くものがあります。大晦日は大つごもり、年の夜とも呼ばれ、この夜は寝ないで、年神様を迎えるために神社などにこもって物忌みする夜不寝講(よねんこう)という習わしがありました。それが元日未明、神社に参拝する風習に変わり、現在の初詣となりました。年越しそばは「細く長く来年も幸せをそばからかき入れる」と言って残さず食べます。 |
 |
 |
松前漬け風 |
|
|
材料(4人分~12人分)
|
スルメ |
・・・ |
1枚 |
| 切り干し大根 |
・・・ |
1袋(100g) |
| 切り昆布 |
・・・ |
1袋(35g) |
| 人参 |
・・・ |
1/2 本 |
| しょうが |
・・・ |
1片 |
| 白胡麻 |
・・・ |
大2 |
 |
| 合わせ酢 |
|
みりん |
・・・ |
1/4 C |
| しょうゆ |
・・・ |
1/4 C |
| だし |
・・・ |
1/2 C |
| 酢 |
・・・ |
大2 |
| 砂糖 |
・・・ |
大1 |
 |
|
|
|
 |
①スルメは焼いてさき、3cm長さに切る。
②切り干し大根は洗って絞る(水に浸さない)
③人参は千切りにし、塩少量でしんなりさせ絞る。
④しょうがは千切りにする。
⑤だしと調味料を合わせ胡麻、切り昆布、①②③④を入れて混ぜる。 |
 |
|
 |
①カリフラワー1個を小房に分けてゆでる。
②酢1/2カップ、砂糖大さじ3、塩小さじ1/2、カレー粉小さじ2を混ぜて①を漬ける。 |
 |
たらこ砧巻き |
 |
①大根をたらこの長さに切り、桂むきして立塩に漬けた後、甘酢に浸す。
②生食用塩たらこを芯にして大根をくるくる巻き、直径3cmくらいにして3つに切る。 |
| |

