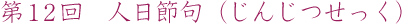 |
|
今年は旬の食材を使って行事食を作ったり、節句にまつわるいわれや風習などを書いてみようと思います。
1月7日を「人日節句」といいます。人を尊重する日です。この日は古来より春の七草を入れた粥を食べる習わしがあります。七草は芹、なずな(ぺんぺん草)、五行(母子草)、はこべら(はこべ)、仏の座(田平子(たびらこ))、すずな(蕪(かぶ))、すずしろ(大根)です。全部揃わなくても若菜をたっぷり入れて粥を炊いてみましょう。 |
|
| |
七草粥はお正月のご馳走ぜめになったおなかを労わり、おせち料理に不足しがちなビタミンCを補います。春の野草は苦みがありますが、この苦みは、春に多いアレルギーの予防になり、又胃の働きを活発にして新陳代謝をアップさせます。
粥は米1Cに対して水5Cを全粥といいます。米1Cに対して水7Cを7分粥、10倍量の水で炊くと5分粥、15倍の水で炊くと3分粥といいます。
今回は簡単にご飯を使って全粥の七草粥を炊いてみましょう。 |
|
| |
|
|
 |
七草粥 |
|
|
材料(4人分)
|
ご飯 |
・・・ |
茶碗2杯 |
| だし |
・・・ |
5C |
| かぶ |
・・・ |
1個 |
| 大根 |
・・・ |
3cm |
| 芹 |
・・・ |
1/2束 |
| 水菜(なずなの代用) |
・・・ |
1/4束 |
| 塩 |
・・・ |
小1と1/2 |
| 醤油 |
・・・ |
小1 |
|
①大根は千切り、かぶは半分に切って薄切りにする。
②芹、水菜は2cmのざく切りにする。
③鍋にだしと①を入れ、少しやわらかくなったらご飯を入れる。煮立ったら弱火で程良く煮て、調味料と②を加え、さっと混ぜて火を止める。 |
|
|
 |
芹の明太子和え |
|
|
| 七草粥で残った芹や冷蔵庫にある明太子などを使って和え物を作ります。鶏ささ身の代わりにカマボコなどでもいいでしょう。 |
材料(4人分)
|
芹 |
・・・ |
1/2~1束 |
| 鶏ささ身 |
・・・ |
2本 |
| 明太子 |
・・・ |
1腹 |
| 酒 |
・・・ |
大1 |
|
①芹はゆでて水にとり4cmに切る。
②鶏ささ身は塩ゆでにして細くさく。
③明太子は袋から出して酒で溶き①②を和える。 |
|
|
~小話~
さて七草ではこんな思い出があります。母や隣のおばさんたちが6日の夜、神棚の前に七草を供えて「はやし歌」を歌うのです。「唐土の鳥が日本の土地(くに)に渡らぬ先に七草なずなでストトンのトントン」と七回唱えながら包丁でまな板をたたきます。この七草たたきの風習は古くから行われている全国的な家庭の行事です。教室でこの話をすると、生徒さんが「この歌、七草粥の時の歌ですか?音感教室の歌かと思った。子供が帰ってきて、この歌を歌うので。」と言うのです。そしてやはりまな板をたたいてするのだそうです。
幼い頃、私は「唐土の鳥ってどんな鳥?」と想像をたくましくしていたのですが、やはり災いを招く妖鳥と聞きます。「夜干しするな、夜爪を切るな」の言い伝えは、この鳥が夜飛び回って悪さをするからといわれ、豊作と健康を祈っての鳥追いの日なのです。唐土とは中国の古い呼び名ですから北風に乗って暖かい南の日本へ渡り鳥が風邪等のウイルスを運んでこないようにという祈りが込められているのです。昔ならスペイン風邪、満州風邪、香港AB型の風邪でしょうか。今も変わっておりません。新型インフルエンザH5N1が昨年は「パンデミックしないだろうか」と国をあげて心配しました。年末には早々にワクチンを接種しましたが、なお懸念をぬぐいきれません。鳥だけでなく飛行機によっても運ばれてきますので国際規模で警戒体制に入っている昨今です。 |

