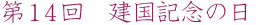 |
2月11日は建国記念の日です。
第2次世界大戦以前は「紀元節」といいました。紀元元年は神武天皇が即位された年として定められました。明治5年、太陽暦(グレゴリオ暦)に改められると、明治7年2月11日(即位日)が紀元節となり、戦争が終わるまでこの日は国民の祝日となっていました。日清・日露の戦争中は勝利の報道などを紀元節にあわせて国家意識を高める日となっていたようです。
昭和15年(1940年)には紀元2600年の祝典が行われ、「紀元は2600年。ああ、一億の胸が鳴る・・・」と歌いました。
昭和20年8月15日(1945年)の終戦で日本は民主主義国家として新しく生まれ変わりました。そして日本国憲法は昭和22年5月3日に発布され、国民の祝日となりました。それ以後「紀元節」は廃止され長い間なくなっておりましたが昭和41年(1966年)「建国記念の日」となり復活し、再び国民の祝日となりました。
昔、紀元節の祝日にはお饅頭が配られました。 今回は、日本の五穀の一つ「きび」を使ってお饅頭を作ります。 |
|
|
 |
きび饅頭 柚子あんかけ |
|
|
材料(6人分)
|
|
きび |
・・・ |
1C |
| 酒 |
・・・ |
大1 |
| 塩 |
・・・ |
少々 |
| A |
|
鶏ひき肉 |
・・・ |
50g |
| みりん |
・・・ |
少々 |
| 醤油 |
・・・ |
小1 |
| |
生姜汁 |
・・・ |
少々 |
|
片栗粉 |
・・・ |
小1 |
| 水 |
・・・ |
小2 |
| |
きくらげ |
・・・ |
適量 |
| |
銀杏 |
・・・ |
6粒 |
| |
栗の甘露煮 |
・・・ |
3コ |
|
だし |
・・・ |
1C |
| 塩 |
・・・ |
小1/3 |
| 醤油 |
・・・ |
少々 |
| みりん |
・・・ |
小2 |
| 葛粉 |
・・・ |
小2 |
| だし |
・・・ |
大1 |
| 柚子 |
・・・ |
1コ |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
①きびはよく洗い、水に一晩浸けておき、せいろで蒸す。2~3回湯をかけ、最後に酒・塩をふる。木杓子で混ぜ3分つぶしして、6等分する。又は、浸けて笊に上げたきびをボールに入れ、水をヒタヒタ(1/2C)に入れて、約30分むしてもよい。
②鶏ひき肉は小鍋に入れ細切りにした木くらげも加えAの調味料を入れて炒り煮して、生姜汁を加え、水溶き片栗粉でまとめ6等分する。
③銀杏はゆでて半分に切り、栗は4つに切る。
④①のきびを平らに伸ばし②と③を芯にして丸めて包み湯気の上がった蒸し器に入れて5分蒸す。
⑤だしに味をつけ濃度をつけておろし柚子を入れてあんを作り、きび饅頭にかける。
※ 饅頭の中実を簡単に、鶏のひき肉だけでも結構です。
※ 蒸したきびを丸め「きな粉」をつけて「団子やおはぎ」にするのもいいでしょう。 |
| |
|
| |
|
|
~小話~
国民学校初等科2年の私の記憶。
紀元節の日は全校児童が静粛に講堂に整列しました。モーニング姿に白い手袋をした校長先生が壇に上り、天皇・皇后両陛下の御真影が祀られた祭壇の白いカーテンを左右に開き、中から漆黒の箱を取り出されました。その箱の中には「教育勅語」が入っていて、校長先生はうやうやしく取り出され厳かに読み上げられました。誰一人乱れる者もなく、咳一つ出す者もいない、それはとても緊張した時でありました。
太平洋戦争が激しさを増した初等科3年生の春、「青少年学徒に賜りたる勅語」を暗記する宿題が出されました。やっとの思いで暗記してそれを発表する日、学校は戦火で焼失してしまい、発表することもかないませんでした。この年(昭和20年)の8月15日に日本は敗戦国となり、第2次世界大戦は終了しました。 |

