 |
6月第三日曜日は父の日。
父への尊敬と愛と感謝を込めて、日本でも戦後暫くして父の日が定着しました。1910年、アメリカのワシントン州でジョン・ブルース・ドット夫人が、男手一つで育ててくれた父に感謝するパーティーを開いたのが始まりだそうです。
又、古代ローマでは、祭りの日には神殿も戦車もバラの花で飾られ、将軍は賞賛のしるしとしてバラの花束を手に持ったと記されています(永田 久氏)。
このような訳で父の日にはバラの花を贈ります。又、私達は音楽会やお誕生日、お祝いの折にはバラの花束を贈ったりします。
昔、日本の父親は寡黙で厳格で一家の大黒柱として家族を守り絶対的な存在でありました。また家族も父親の言うことには全員がそれに従う姿勢は崩れることがありませんでした。両親は、家庭で箸の持ち方から始まり食事のマナーや挨拶、早寝早起き、規則正しい生活、善悪の判断、物事の常識、勤労の尊さ、上下のわきまえ等を幼児期より教えるのでした。戦後男女平等になり、家庭における父親の存在は女親と同等となったようですが、まだまだ日本の父親の存在は大です。
父が今頃になると釣ってきた、“カレイを薄作り”にしました。梅肉醤油で召し上がってください。写真に掲載しました。 今回は今が旬の*じゅんさいと白玉団子でのどごしの良い酢の物を作ってみました。 |
|
|
|
 |
材料(6人分)
|
| |
|
じゅんさい |
・・・ |
2袋 |
| |
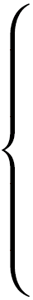 |
白玉粉 |
・・・ |
1C |
| 水 |
・・・ |
1/2C強 |
| 塩 |
・・・ |
少々 |
| |
|
土佐酢 |
|
|
| A |
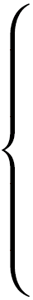 |
酢 |
・・・ |
1/2C |
| 水 |
・・・ |
大2 |
| 砂糖 |
・・・ |
大2と1/2 |
| 薄口醤油 |
・・・ |
小2 |
| 削り節 |
・・・ |
3g |
| |
|
生姜汁 |
・・・ |
小1/2 |
|
|
| |
① じゅんさいは笊に入れ、熱湯をかけ、ただちに冷水をかけて器に取る。
② 白玉粉は水で耳たぶ位の柔らかさにこね、一円玉大に丸めて茹でる。
③ 土佐酢はAの調味料を煮立てて布巾で絞ってこし、冷やして生姜汁を落とす。
④ ガラスの小鉢6個に①と②を等分に入れ③の土佐酢をかける。青みに山椒の実を飾ってみました。 |
|
| |
|
| |
*じゅんさい
結婚して間もない頃、浜松駅から呼び出しがありました。「貨物列車で北海道から何やら薬らしいものが届いたので見に来てください。」という電話です。行ってみると薬の缶からぬるぬるとした液体が出ていました。開けてみると中にはたくさんのじゅんさいが入っていました。主人の実家も医師でしたので薬の空き缶だったのですが、じゅんさいを見たこともない駅員さんは不審がり、釈明するのに大変でした。じゅんさいはスイレン科の多年草で100年以上清い水の湧き出ている沼に自生します。函館近くの大沼公園の中のじゅんさい池で取れたものを義母が送ってくれたのでした。 |
|
| ~小話~ |
父のこと、子どもの食事について
父は趣味の多い人で、裏庭で弓を引き、的を目がけて矢を放っていました。待合室にはどっしりとした碁盤が置いてあり、患者さんと一局混じえていました。お座敷では、日本刀の刀身に白い粉(打ち粉)をパタパタ打ってぬぐい、ピカピカにして眺めていた姿を思い出します。また診療の合間をぬって裏隣りの家で球つき(ビリヤード)をしていて、「患者さんが5人になったら呼びに来なさい。」と言うのです。お酒をこよなく愛し、書画、俳句を嗜み、庭の松の木をとても大切にしていました。その中でも特に好きなのは魚釣りでした。潮の良い日には朝3時に起きて漁師顔負けの出で立ちで和舟を漕ぎ出し、流し釣りをしていました。カレイやコチ、黒鯛などびく一杯持ち帰ることもしばしばで家族は季節ごとの生きのよいお魚を食べることができました。
こんな父の欠点は並外れた子煩悩です。庭に砂場を作り、鉄棒を備え、裏庭に続く通路には大きなブランコが作られていました。屋敷内には子ども達に果物を食べさせようと、桜んぼ、夏みかん、桃、びわ、いちじくの木が植えられ、立派な実を生らせていました。春には毛虫を焼いたり、タバコの吸い殻から抽出したニコチン液で消毒したり、鰹のあらを煮て肥料にしたりして大切に育てていました。花が咲き、青い実になると人を雇って袋がけをさせ、虫の予防をします。桃の木は4、5本あり、蜜をたっぷり含んだ大きな桃を毎日5個も6個も食べました。夏みかんは私のために植えられたようで学校から帰ると蠅帳の中にむき身の砂糖がけが丼一杯入っていて、これが私の毎日のおやつ。「お前は色黒だからビタミンCを取るように」という訳です。更に夕食前にもう一つのノルマがありました。レバー焼き2本です。「お前は頬の色が悪いから赤くなるように」と鉄分の補給です。弟は牛乳、妹は卵など。一人ひとりの子どもの様子を見ながら体調を整えるのが父と母の子育ての基本であったようです。
幸なことに実家は東海道、舞阪宿の名残をとどめており、近くに肉屋、牛乳屋(牧場)、氷屋(製氷所)、料理屋、宿屋、カフェなどがあり、食材が豊かでした。この地は停車場(ば)と呼ばれ、雄踏の人は自転車で、村櫛半島の人々は渡し舟に乗ってこの舞阪駅から通学したのです。 |

