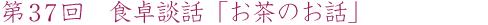 |
 |
| 秀吉が鷹狩りに出た時のこと、咽喉(のど)が渇いたのである寺に立寄って茶を所望(しょもう)した。早速、愛らしい小姓が大きな茶碗に温かい加減の茶を七、八分目注いだのを差し上げた。秀吉はさも快(こころよ)げに咽み終わり、更にお替りを所望した。今度は幾分湯加減が熱々、量は茶碗に半分くらゐであった。前の一碗で一応の渇きは止まってゐるから今度は徐々に喫(の)む。喫み終った秀吉は、またお替りを所望した。此度は前二回と異なって茶碗が小さいのと取換へられてあり、湯加減も前回よりは一層熱く、量も頃合いに注いである。三度が三度とも度(ど)に適(かな)った湯加減と分量。秀吉は、ぢっと小姓の顔を瞶(みつ)めてから、住持(おうぢ)に向って「此の小姓を余に呉(く)れまいか。」と請(こ)うて連れ帰った。この小姓が石田治部小輔三成(ぢぶしょういみつなり)である。 |
|
|
|
| ~私の感じること~ |
このお話は茶の湯を嗜(たしな)む方々には、すでにご存知の逸話です。
茶の湯で出されるお茶は碾(てん)茶を石臼で挽(ひ)いた抹茶が用いられます。この碾茶は樹木の下生えとして育つ日陰に強い性質を持った茶の樹を極限的ともいえる高度の品質管理のもとに造られる高級茶です。普通茶(やぶきた茶等)に比べて最も異なるところは、新芽の成長期に長期に渡って被覆を行い、日射しをさえぎって緑茶の持つ旨味成分のテアニンを更に増加させるところです。製造には技術・管理に加え、被覆柵などの設備も大変なので産地も限られています。主に宇治市、静岡県では岡部町(藤枝市)などです。 |
|
|
先日、夫の運転で岡部町小園の「玉露の里」を訪ねました。山里の段々畑には、そこかしこに黒い被覆が張られていました。組合長様のご案内で大きな大きな被覆柵の中に入ると目にも鮮やかな新芽が一斉に出揃っていました。あと一ヶ月位は光も風も当てないようにするのだそうです。
「玉露から碾茶に作柄を替えて、やっと町興しが出来た」と、言っておられました。碾茶工場を見学させて頂き、帰りには抹茶のお土産まで頂戴し、感謝致しました。
お茶は抹茶も普通茶も半熟成で製品になっていますので、夏の土用を越して熟成し、秋においしくなります。茶の湯では11月が茶人の正月といわれるゆえんです。
茶園と茶の製造業を営んでいた義兄(「まぼろしのお茶を追う男」家庭画報社)が、「新茶のころに古茶を買いに訪れるお客さんが一番こわい。その頃、古茶は新茶の香りがするのだよ。お茶はそのように造られなければならない」と、言っていたのを思い出します。
お茶造りの奥深さを知った言葉です。
|
|
|
先日、日本国籍となられた海外産まれの女性が料理教室に入学したいと訪ねてこられました。一旦、自宅にて面接致しました。客間からお庭を眺めて「京都に行ったよう」と、つぶやいていました。明朗できちんと社会生活をしておられる女性とお見受け致しましたので、お教室に御案内しました。
古い古い日本座敷の初釜の風情の残るお座敷で和菓子と抹茶を差し上げました。「日本に来て12年経ちましたが、やっと日本に来た(日本に逢えた)気がします」と、感慨深げでした。「日本文化を知りたいのですが、何から習ったら良いのか解りませんので、まず、日本料理を習いたいです」と、懇願されました。
一服のお茶がとりもつ日本文化への掛け橋になればと思い、受け入れたいと思っています。
|

